医療費を抑えるコツ
病気やケガは突然やってきます。特に、収入が限られている時期に病院へ行くと「この支払いどうしよう……」とため息をつく人も多いはずです。
しかし、制度を正しく理解しておくことで、同じ治療を受けても支払う金額をぐっと減らせます。この記事では、実際に低収入で暮らしている筆者が活用している制度や、知って得する支援の仕組みを、できるだけわかりやすく整理しました。
1|高額療養費制度を徹底理解する
まず押さえておきたいのが高額療養費制度です。これは、1か月にかかった医療費の自己負担額が上限を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
「そんな制度あるの?」と思う人も多いですが、全国民に適用される健康保険の基本制度です。申請すれば誰でも利用できます。
自己負担限度額の詳細
下の表は、所得区分ごとの月あたり上限額の目安です。入院や手術などの高額医療のときに特に効果を発揮します。
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 特徴 |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 生活保護に近い層を対象。年金生活者や無職世帯が該当しやすい。 |
| 年収約370万円以下 | 57,600円 | 一人暮らしや非正規労働者など、比較的低所得の層。 |
| 年収約370〜770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 標準的な中間層。 |
たとえば入院して医療費が20万円かかった場合、低所得世帯なら35,400円を超えた分があとで返金されます。つまり、実質負担は2割以下で済むこともあります。
限度額認定証を事前に入手する
高額療養費はあとから申請して払い戻してもらう方法もありますが、最初に全額払うのは負担が大きいですよね。そこで便利なのが限度額適用認定証です。
この証書を病院窓口に提示すれば、最初から上限額だけの支払いで済みます。役所や健康保険組合で簡単に申請できます。
- 国民健康保険 → 市区町村役場
- 社会保険加入者 → 勤務先または健康保険組合
筆者も過去に入院した際、認定証があったおかげで支払いは4万円ほどで済みました。申請していなければ、十数万円を立て替えるところでした。備えあれば憂いなし、です。
2|自治体が用意している医療費支援を知る
実は、国の制度だけでなく、市区町村独自の医療費助成制度がたくさんあります。しかも、全国どこでも申請は無料です。
代表的な自治体支援制度
- 国保料の減免制度: 失業・廃業などで所得が激減した場合、国民健康保険料の一部が減額されます。
- ひとり親家庭・障害者医療費助成: 自治体ごとに対象条件が異なりますが、自己負担が1割〜無料になることも。
- 重度心身障害者医療費助成: 障害手帳を持っている方や難病指定患者への助成。
これらは「申請しないと適用されない」点に注意が必要です。役所の窓口で「医療費の助成制度を教えてください」と聞くだけでOK。対象者なら案内してくれます。
実際の申請体験談
職員「お仕事は現在されていませんか?」
筆者「はい、失業中です。」
職員「それでしたら、保険料減免の対象になるかもしれません。こちらの申請書に記入をお願いします。」
筆者「書類は多いかと思いましたが、以外と簡単なんですね」
このように、役所の窓口は想像よりも親切です。むしろ「来てくれてありがとう」という態度の職員も多い印象です。
3|確定申告で医療費控除を受ける
1年間に支払った医療費が合計で10万円(または所得の5%)を超えると、医療費控除が受けられます。申告すれば税金が一部戻ってきます。
対象になる支出の例
- 病院・歯科・整体・鍼灸などの治療費
- 通院のための交通費(電車・バス)
- 医師が処方した薬代
- 眼鏡・義歯・補聴器(治療目的の場合)
- 家族の医療費(生計が同じであれば合算可)
確定申告はスマートフォンからも可能です。マイナンバーカードとマイナポータル連携を使えば、ほとんどの病院データが自動で反映されるようになっています。
控除の申請をしない人がまだまだ多いですが、1万円〜数万円単位で戻ることも珍しくありません。
4|薬代を減らす具体的テクニック
① ジェネリック医薬品の活用
薬局で「ジェネリックありますか?」と聞くだけで薬代が3〜5割安くなることがあります。効果や成分は同じで、副作用のリスクも同等です。なぜジェネリック医薬品が安いかというと、新薬の特許期間が切れた後に製造されるため、新たな開発費や特許費用がかからないからであって、品質は担保されています。
② ドラッグストアのプライベートブランド医薬品
ツルハ、マツキヨ、ウエルシアなどのドラッグストアには、自社ブランドの風邪薬や胃薬が揃っています。価格は大手製品の半分程度。体調管理コストを大幅に抑えられます。
③ セルフメディケーション税制を活用する
健康診断や予防接種などを受けている方を対象、年間12,000円以上の市販薬購入がある場合、確定申告で税金の一部が戻ります。申請にはレシートの保管が必要なので、箱にまとめておくと便利です。また全ての市販薬が対象ではないので、常備薬が該当するかどうかチェックしてみるといいでしょう。
5|健康保険料を減らす方法も知っておく
意外と見落とされがちなのが、保険料そのものの減免です。自治体によっては「国民健康保険料の減免・猶予制度」があります。
対象となるケースは、失業・病気療養・災害・事業廃止など。自治体によって運用が違うので、利用したい方はお住まいの区役所などに相談してみるといいでしょう。
この申請も役所の「保険年金課」で行います。住民税の非課税証明書を添えるだけでOKです。
非課税証明書はお住まいの市区町村の役所の窓口、郵送、もしくはマイナンバーカードを利用したコンビニ交付で取得できます。手数料は300円です。
6|医療費を日常的に減らす生活の知恵
制度のほかにも、日常生活の工夫で医療費を減らす方法があります。
- 体温を上げる生活(冷え対策・湯たんぽ・温かい飲み物)
- 定期的な軽い運動(ウォーキング・ラジオ体操)
- 口内ケアを怠らない(歯の治療費は高額)
- 市販薬は最寄りの薬局よりネットで買う方が安いケースが多い。amazonのセールなどで常備薬をチェック!
病気を未然に防ぐことこそ、最大の節約です。筆者は毎日30分のウォーキングとスクワット50回、歯磨きだけはかかさずやっています。
7|自治体の「健康ポイント制度」も見逃せない
最近は、健康管理を促進するためにポイント制度を導入する自治体も増えています。
スマホアプリや記録用紙でウォーキングの歩数を記録し、一定の基準を満たすと商品券などがもらえる仕組みです。東京都、名古屋市、大阪府などで実施されています。
筆者の住む地域でも、1年間の健康記録を提出しただけで「地域商品券2,000円分」をもらえました。こうした制度は“節約と健康の両立”に最適です。
まとめ|医療費を減らすという「知恵の節約」
医療費の節約は、単にお金をケチることではありません。自分の生活を守るための知識を持つことです。
高額療養費制度、限度額認定証、医療費控除、自治体の補助。どれも申請しなければ得られません。知らないだけで損している人が多いのです。
これらを一つずつ確認していくだけで、医療費負担は確実に減ります。健康でいること、制度を知ること。どちらも同じくらいの「節約力」です。
無理をせず、使える制度は遠慮なく使う。これが、低収入時代を生き抜く現実的な知恵です。
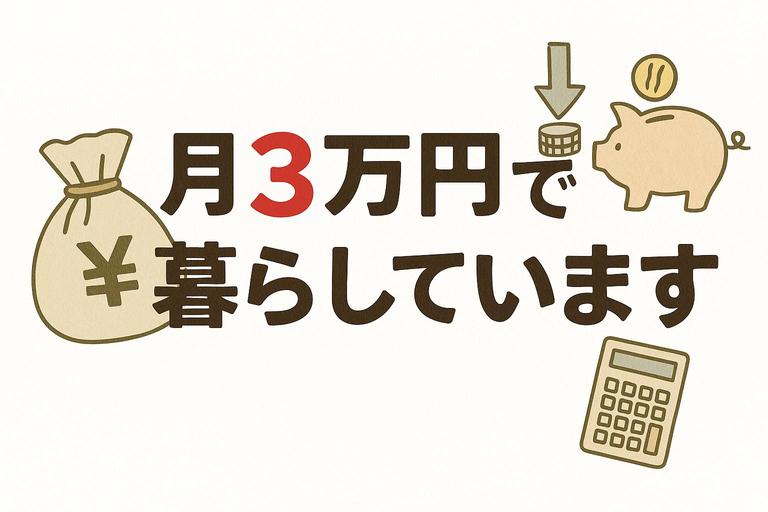
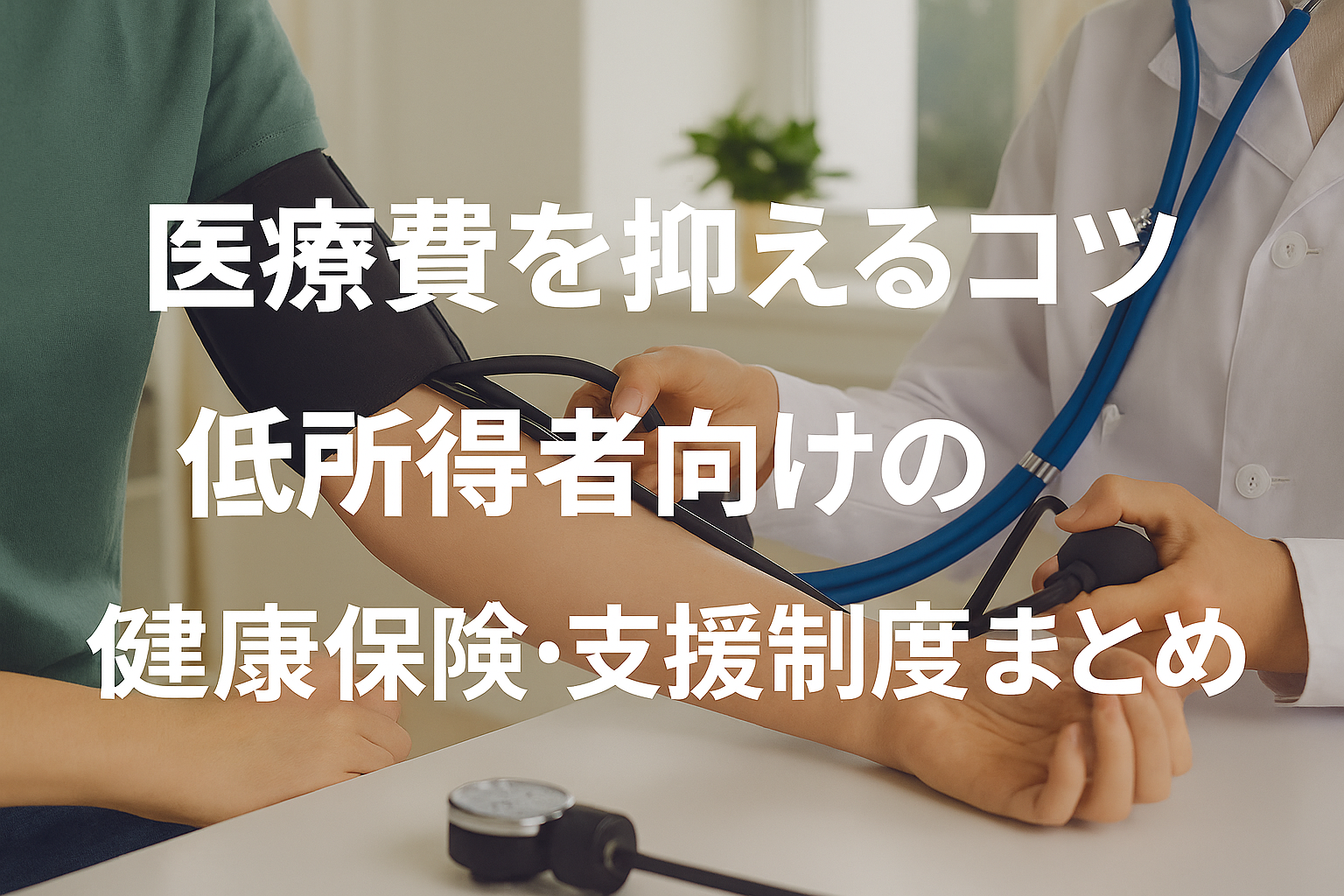

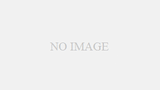
コメント