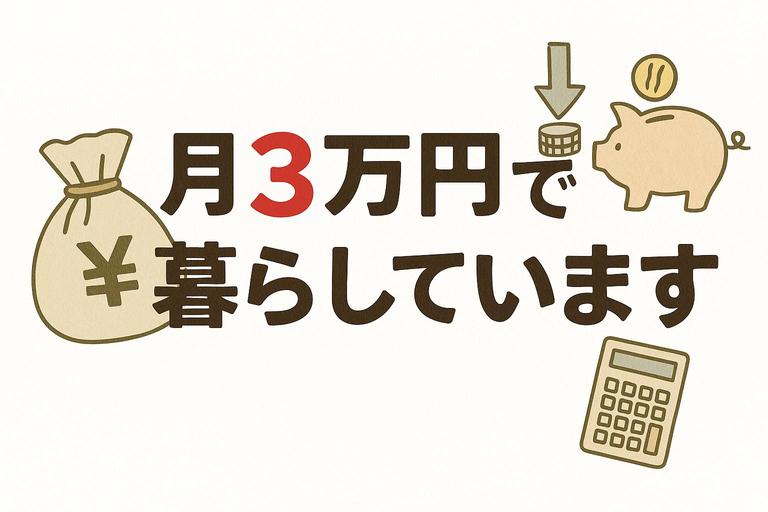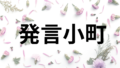SNSを開いた瞬間、どこか心がざわつく。
人の成功、自分の不足、誰かの愚痴、そして「いいね」の数。
静かに暮らしたいと願う人ほど、SNSに疲れてしまうのは自然なことです。
今回は、SNSとの距離を見つめ直し、心を守るための“静けさの使い方”を考えます。
1. SNS疲れは「情報疲れ」よりも「感情疲れ」
私たちが疲れる本当の理由は、情報量ではなく感情の同調疲れです。
タイムラインには、嬉しい報告、怒り、不安、愚痴など、無数の感情が流れています。
その感情の波に無意識に巻き込まれているうちに、自分の心のリズムを見失ってしまう。
だからこそ、まずは「誰の感情を見ているのか?」を一度切り分けてみましょう。
- 心が揺れる投稿は、一時的にミュートする
- “共感”よりも“観察”の目で眺める
- いいねの数を「他人の拍手」ではなく「背景音」として受け流す
感情の同調を止めた瞬間、SNSはただの「情報の流れ」に戻ります。
そこから静けさが戻ってきます。
2. SNSを「見る時間」ではなく「使う目的」で決める
多くの人は「SNSをどのくらい見るか」で疲労を測ります。
でも本当は、“なぜ見るのか”が曖昧なことこそが、心を消耗させます。
- 「学びのために10分だけ見る」
- 「知人の近況だけ確認して閉じる」
- 「発信する時だけ開く」
こうして目的を明確にすると、SNSは“道具”に戻ります。
何となく開く時間がなくなると、意識が現実に戻り、生活の密度が上がるのです。
3. SNSをやめるのではなく、「現実を増やす」
「SNS疲れた、もうやめたい」と思う人は多いですが、完全に断つ必要はありません。
むしろ、SNSより現実の比重を増やすことが一番の処方箋です。
- 短い散歩やウォーキングで“音のある現実”を思い出す
- 手を使う行動(料理・掃除・メモ)で「自分の世界」を再構築する
- 現実の人間関係を1人でもいいから“顔のある関係”にする
現実が薄いとSNSが濃く感じられ、 現実が濃くなるとSNSは自然に“背景”へと退いていきます。
4. SNSを「静けさの訓練の場」に変える
静けさの哲学の視点から見ると、SNSは心を試される修行の場でもあります。
誰かが怒っていても、比べていても、自分は穏やかに観察できるか。
その姿勢こそ、静けさの実践です。
たとえば、SNSを見ながら深呼吸を3回する。 1分間スクロールを止めて、「いま自分はどんな気持ち?」と確認する。 たったそれだけでも、情報の波を中から見られるようになります。
5. SNSを閉じたあとの「余白」を育てる
SNSを閉じた直後に、心の中に少しの空白が生まれます。
その時間を埋めるように別のアプリを開くのではなく、 そのまま静けさの余白として味わう習慣を持ってみましょう。
お茶を淹れる。ノートを開く。外の風を感じる。
「情報の海」から「現実の空気」へ。 この切り替えの一瞬にこそ、心を癒やす力があります。
🌿 まとめ
静けさとは、情報を断つことではなく、情報に飲まれない技術です。
SNSを閉じたその後に、何を感じ、どう過ごすか。 その選択の積み重ねが、あなたの中の静けさを育てていきます。